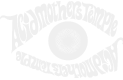いよいよDaevid Allenとのユニット「GURU & ZERO」のミニUSツアーも差し迫り、これにさえ出発してしまえば、しばらくは日本の夏ともお別れにして、されど未だAMTの新作全ては完成しておらず、取り敢えず2枚のフルアルバムと4枚のシングルは、何とか完成に漕ぎ着けたが、あと残す処スタジオ録音フルアルバム1枚、ライヴ盤1枚を完成させねば、我が夏の終わりは告げられぬ。来たる22日の出発までに、せめてスタジオ録音フルアルバムだけでも完成させてしまいたいものであるが、果たして如何なものか。そもそも新作アルバム4枚同時リリース等と云う暴挙にも近い計画も、己れで仕組んだ事なれば、リリースしてくれるレーベルに感謝こそすれ、文句なんぞ垂れられる筈も道理もなし。
されどこの忙殺されそうなハードスケジュールの中であろうと、僅かな暇を見つけては、近所の古本屋「オリオン書店」を覗いてしまい、テオ・アンゲロプス研究/フェリーニの都製作ドキュメント等の特集が組まれている「イメージフォーラム」のバックナンバーやら、「背中まるめて~『小沢昭一的こころ』のこころ」やら、そして官能小説の巨匠である宇能鴻一郎著「セクハラ大好き」等を、ついつい購入している有様。
小学生の頃から、私はこの宇能鴻一郎の大ファンである。彼の存在を知ったのは、夕刊フジでの連載であった。父が持ち帰る夕刊フジを、翌日ゴミ箱からこっそり拾い上げ、エロページのみを隠れて読み耽っていた私は、そこに連載されていたあまりに奇妙な文体の官能小説に一瞬で虜にされてしまい、それ以来毎日、父が持ち帰る夕刊フジを心待ちにしたもので、時折持ち帰って来ぬ日があれば、翌昼に駅のキオスクまで出向き、わざわざ買い求めたりもした。(「夕刊」なので昼に行けば前日号が残っていた。)挿し絵は杉浦幸雄と云う、何とも肉感的女性を描く方で、宇能鴻一郎の描く「肉感的な女性」とあまりにぴったりマッチしており、また時折コミカルな表現の文章を、そのまま挿し絵化してしまう感覚(男根が「ジャンボジェット」と例えられた折、本当に「女性の顔と巨大なジャンボジェットの機首が向き合っている図」を描いていた)こそ、宇能鴻一郎の世界を描くに相応しい等と、子供ながらにも感心したものであった。
当時(昭和50年頃)夕刊フジに連載されていた、私が宇能鴻一郎と初めて出会った記念すべき作品は、現在私の所蔵する宇能鴻一郎コレクションにも見当たらぬ上、 その作品名がどうしても思い出せず、ただOLが会社の慰安旅行で行った温泉にて、入浴中に前後から同時に上司2人に犯られる等と云う、至って有りがちな話ではあったのだが、自分にとっては「宇能鴻一郎初体験作品」であるが故、何とかもう一度読みたいと思う次第である。
この作品に続いて連載された「あつく湿る」は、団地に住む新妻の話であり、確か改題されて単行本化された筈である。これも持っておらぬので、何とか探したいと思い古本屋を巡るのであるが、宇能鴻一郎の作品なるもの、買えども買えども見知らぬタイトルを発見する。一体今までに、彼は何冊の本を出版しているのか。ネットで検索をかけてみても、矢張りと云うか当然、宇能鴻一郎のオフィシャルサイトなんぞ存在せず、残念ながらファンサイトもなければ、せめて作品一覧ぐらいはと思うのだが、それすらも見つけられず。更には別名による推理小説やエッセイ、翻訳までもあるそうで、その膨大な作品リストを把握するのは、ほぼ絶望的かもしれぬ。
官能小説なんぞ、夕刊フジやらスポーツ紙、大衆週刊誌等に掲載され、サラリーマンの帰宅途中の電車内での御伴として、読み終えた後は網棚に放置されるか、駅のゴミ箱に捨てられるかの末路を辿る、まさしくゴミ同然にして、到底文学としては認知されておらぬであろう。単行本も星の数程出版されてはいるが、そもそも読者に文学として認知されておらぬ、所謂消費文化の一端を担っておればこそ、哀しいかな名作として後世まで残される事もなく、精々廃品回収業者が、鄙びた古本屋に目方幾らで卸した中にひっそりと紛れ込んでは、店頭に並ぶ程度であろう。かつて官能小説の二大巨頭であった川上宗薫と宇能鴻一郎の作品でさえも、今では古本屋の官能小説コーナーでお目にかかる事さえ稀であり、如何に官能小説たるものが、その文学的価値を認識されておらぬかを、ここに思い知らされる。
しかしネットで検索しているうちに、実は意外にも文学を愛する人達の「裏フェイバリット」として、かなりの支持を得ている事が発覚。「隠れ宇能鴻一郎ファン」の多さに驚きつつも、矢張り彼の官能小説界に於ける功績は図り知れぬ事、これは本当に間違いないであろうと実感。
宇能鴻一郎とは、川上宗薫と並ぶ日本の官能小説の巨匠にして、彼が編み出した唯一無比の文体「女性独白体(『一人称官能ロマンシリーズ』と呼ばれているらしい)」は、それまでのありとあらゆる官能小説の常識やタブーを打破し、明らかに官能小説界に革命を起こしたと言える。何でもその句読点と改行の多さから「余白小説」とも呼ばれているらしいが、確かに3行に跨がる長い文章等まず見掛けぬ上、稚拙な会話文が非常に多く、もしやこれこそ当世の若い女性の独り言口調ではなかろうかと、まるで女性の日記でも覗いたかのような錯覚から、世の男性諸氏は下半身を熱くさせずにはおられぬ程に、これぞ究極の官能的文体であろう。そしてこの宇能鴻一郎は、勿論近頃横行する素人に毛の生えた程度の文才しか持たぬ凡百の「エロ作家」とは全く異なり、天賦の才能があるが故にこそ、この一見稚拙にさえ思える魅惑の文体を、見事完成し得たのである。
宇能鴻一郎ファンなら誰でも知っている事であるが、彼の文筆活動は官能小説から始まった訳ではない。彼は東大大学院国文科に在籍中、「鯨神」で昭和36年下期の第46回芥川賞を受賞し、久々に現れた日本純文学界の大型新人として期待され文壇に登場したのである。その後「地獄銛」「閻浮の秋」等の純文学作品を発表するが、次第に「密戯」「痺楽」「痴戯」「逸楽」「魔楽」等の官能作品へ転向、そして現在の女性独白体に因って、遂に官能小説の頂点へ登り詰めたのである。
かつて国内外の文豪と呼ばれる巨匠達が、変名で官能文学の名作を生み出した事を思い起こせば、芥川賞作家である宇能鴻一郎も、矢張りその文才を認められ、昭和官能文学の名作として、彼の大全集が出版されて然るべきであろう、と思うのは私だけか。
宇能鴻一郎の女性描写には、必ず「肉感的」である事が強調され(「女ざかりの、ムチムチ」「骨細だけれど、お乳もお尻も大きくて」「スラリと痩せてるけれど、お乳とお尻はプリン、と発達してて」「丸みのある固太りの肉体、けっこう魅力的らしいけれど」「色白で、ムッチリした肉体をしてるんだけれど」「腕も腿も健康に張りきった、ピチピチした」「ムチムチプリンの」「お乳も腰も、自分でもうっとりするくらい、脂肪が張りつめているし」等)、一方容姿は「顔はあまり、美人じゃないけれど、小さくて。」と云う下りが毎度見受けられる。またほぼ全作品に於いて主人公の女性を語るにあたり、まだ「フェロモン」なんぞと云う単語さえが蔓延する以前から、日本人には然程縁のない「体臭」についても、常に「汗」を用いて何ともリアルに「女性の肉体の香」を描写する事により、よりリアルにその女性の肉体を読者は嫌でも感じざるをえないのである。これには如何に昨今のエロ作家達が、様々な「使い古された」語彙を並べようが、全くこの足元にも及ばぬであろう。何せ宇能鴻一郎が使う語彙と云えば、女性独白体であるが故、女性が使えば違和感のある通俗的且つ卑猥なものは当然避けられ、至ってシンプルに単刀直入、更に回りくどい隠喩めいた表現も一切なく、それらをあの稚拙さ極まりないような女性独白体で綴る事により、よりリアルな芳香溢れる女性の肉体がそこに描かれるのである。これこそ「誰でも書けそう」で実は「誰も真似出来ない」、まさしく「官能小説の奇跡」とも言える宇能鴻一郎の真骨頂であろう。
女性独白体を完全に完成させたのは、矢張り作品の書き出しが「あたし、女子高校の三年生なんです。」と云う、自己紹介的な内容になってからと思われる。冒頭でその主人公が、自分のキャラクターを明言する事で、読者は本題に入る前に、その女性の容姿や年令・職業等を容易に掌握出来、自分の頭の中に、その女性像を完璧に想像する事が出来る。これは官能小説と云う、読者のイマジネーションが最も大きなポイントとなる分野では、絶対的命題であるが、それをいとも簡単に最初の5行で完結させてしまうとは、全く恐るべき手法である。かつて友人宅にて、何げに置かれていた夫婦生活系雑誌を手に取った処、投稿による夫婦の営みやらが赤裸々に綴られており、大いに興奮して読み進めておれば、最後に投稿者の年令が70歳であることが発覚、これには流石についぞ今さっきまで興奮していた気持ちが萎えるどころか、何故斯様な重要な事柄を予め書いておかぬのかと、自分のきまり悪さを棚に上げて、大いに憤慨したものであった。勿論、宇能鴻一郎のこの手の作品では、斯様な事態は起こるべくもなく、読者は常に安心して、自分のイマジネーションを拡げ、その甘美な世界に身を委ねる事が出来るのである。
この一見大した事でもなさそうな書き出しさえも、実は官能小説たるべく必然性に裏付けられて書かれており、更に独白体であればこそ成し得た天才ならではの技であろう。
官能小説は、先ず大衆文学でなくてはならず、文盲でない限りは、誰もが理解出来る文章でなければならない。また口説くプロセスから衣服を脱がせ、いよいよ事に及ぶまでの流れのスピード感を、見事コントロール出来てこそ一流の官能小説家と呼べるであろう。仮想現実であれ、読者にとってはリアルである事こそ、官能小説の命であるのだから、難解語句やらあまりに抽象的比喩は、読者の昂る気持ちに水を差すだけの結果しか生まぬ。その点、この宇能鴻一郎の文体は、当時小学生の私でさえ何の無理もなく理解出来たどころか、まだ毛も生えておらぬガキの股間さえ熱くさせるに余りある程で、これぞまさしく究極の官能小説であろう。
若者の活字離れが叫ばれて久しいが、ならばせめて官能小説でも読ませてはどうか。アダルトビデオの蔓延により、若者の性に対する想像力が極端に低下しているとか。妄想する愉しみを知らぬとは、人間として生まれ落ちた歓びを放棄しているようなものである。ただセックスするだけであれば、猿でも出来る。妄想するからこそ、より性の歓びや哀しみを知り、そして新たな世界も見えて来るのである。
何でも森鴎外や夏目漱石の作品が、国語の教科書から消えたそうだが、では一体これからの世代は、近代日本文学さえも知らぬようになる訳で、「日本語の崩壊」と云われている昨今、遂には日本語も英語のように「味も素っ気もない」表現力の狭い言語になり下がってしまうのか。
ならばである、宇能鴻一郎のこの一見ふざけたような文体の奥に潜む、真の日本語の奥の深さを探りつつ、男子生徒は「ムクムクと、大きくなって」「おまけに、ピクン、ピクン、と脈打って」「コーフン」するような、女子生徒は「あたし、たちまち感じてしまって、ジュンとあふれて」「ウットリ」するような国語の授業をして頂きたい。
そして出版社各位には、是非とも宇能鴻一郎大全集を出版して頂きたい。出来れば杉浦幸雄の挿し絵も完全収録で。かつて国枝四郎の本を探していた頃も、「神州纐纈城」以外絶版と云う事態に、日本出版界の怠慢とも云うべきその実状に大いに憤慨したものだが(その後国枝四郎全集は復刻された)、まだ一度たりとも刊行されておらぬ宇能鴻一郎大全集を、どこかの出版社が英断してくれぬものか。今やアングラと呼ばれた60sや70sの映画やレコードや漫画等は復刻されておれど、その当時の社会を支えた企業戦士たるサラリーマン諸氏に、ひとときの安らぎと甘美な夢を与えていた、日本裏文学の最高峰とも言える宇能鴻一郎の官能小説、果たしてこのまま時代の流れに葬ってしまって良いものか。
今一度、宇能鴻一郎に世の光を。
(2002/8/16)