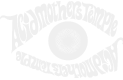今回のツアーは「Acid Mothers Temple Soul Collective Tour 2003」と題された「つるばみ」「Pardons」「河端一 solo」の3部構成となった企画モノで、1ヶ月間でアメリカ(San Francisco / Chicago)~イギリス~アイルランド~フランス(Parisのみ)~アメリカ(New York / Philadelphia / Seattle)を巡ると云うもの。いつものAMTのツアーとは異なり、久々に「地道な」ツアーであった為、いろいろと思う事多数。
拠って今回は「ツアー四方山話」的な内容で綴ってみる事にする。
第90回「Who’s next?」
ツアーに出掛ければ、多くの友人との再会も叶い、また新たな人達とも出会う。
特に今回は、多くの年季の入ったGongファンに出会う事となった。単に私とCottonがDaevid Allen率いる新たなGong「youNgong」のメンバーであると云う事があってであろうが、かれこれ30年以上Gongを追い掛け続ける彼等は、Dead Heads同様、世界中にネットワークを持っているらしく、況して今やインターネットの普及もあり、驚くべき情報収集力を保持しているようである。先達てのイラク戦争の折も、65歳になるDeavid Allen自身が、反戦運動をインターネットを駆使してワールドワイドに展開していた事からも、Gongファミリーがインターネットをひとつの「手段」として活用している事は明白。私にすれば、いい歳のヒッピー親爺共がPCに向かっている姿より、旧態依然のナチュラリスト然としたヒッピー像を想像しがちで、私よりも余程コンピューターを上手く活用しているグローバルな姿を見るにつけ、若い我々の方が「時代から取り残された」古臭い旧タイプである事を痛感。HD録音にしてもどうにも取っ付きにくく、未だ手付かずでチンプンカンプンな私なれば、矢張り「リアルタイム」ヒッピーである彼等の「新しい流れ」に対する抵抗感の希薄さは、激動の時代を生き抜いて来たからこそなのであろうか。また世界中に拡がるGongファミリーなればこそ、インターネットの利用価値にいち早く気付いたのやも知れぬ。
と云う訳で、今回はヒッピー親爺連中と懇意になる機会が多く、一方で客筋はより一層胡散臭さを増し、可愛い若い女性もいるにはいるが、開演前や終演後に近寄って来るのは、殆どがヒッピー親爺なのである。今回のツアーに於いて、一体どれ程のヒッピー親爺達の記念撮影に応じた事か。意外にも彼等はミーハー的である。
斯様な流れから、ウェールズで泊めてもらった家は、ヒッピーコミューンであり、更に隣人はHawkwindのNik Turnerであった。御陰でこの夜のコンサートでは、Nik Tunerがサックスとフルートで客演する運びとなり、楽しい「Space Jazz Session」と相成ったのであるが。残念ながら例のコスチューム姿ではなかったにせよ、全身ブラックのレザースーツに身を包んだNik Turnerは、佇まいが他のヒッピー親爺とは全く異なり、恐ろしい程「Rock」であった。いざステージに上がって来るや、徐ろにサックスを吹くのかと思えば、何やら躊躇している様子。しばらくして胸ポケットから思い出したかのようにサングラスを取り出し装着するや、エコーかけまくりの例のNik節が炸裂。これは演出なのか、さてまた忘れていただけなのか。ここからはまるで「宇宙遊泳」の如き浮遊感溢れる世界が展開され、それは「始まり」も無ければ「終わり」もない、これこそ矢張りHawkwindならではの時間感覚なのか。そもそも1セットのつもりが、2セットとなり、果ては終演後も「もう終わりなのか?もっと演奏しよう!」と、クラブの閉店時間さえお構いなし。何はともあれ楽しいひとときであった。一部の客やスタッフから「Acid Hawks Gong」の結成を切望されたが、もしも斯様な奇跡が起きたなら、長年に渡る両バンドのファンである私にとっては、もう「感慨ひとしお」なんぞと云う騒ぎではなかろうて。
さてそのもう一方のGongであるが、今秋予定されていたyouNgongの欧州ツアーは来春に延期される様子。今年後半は、10月から年末までの3ヶ月間はツアーに明け暮れるのかと思い、溜まりに溜まったAMTやソロのレコーディング予定をどう捌こうか思案に暮れていた矢先であった為、この延期決定は、私にとっては朗報であった。そんな中、今回のツアーに於いて、LondonとBrightonの2ケ所で、Daevid Allenとのユニット「Guru & Zero」のライヴを特別セットとして行った。DaevidとCotton、そして私のトリオによる即興ユニットである「Guru & Zero」は、今年中にはイギリスのSwordfish RecordsからCDとLPをリリースする予定。爆音インプロトリオ「つるばみ」の後に演奏した為、Daevidが非常にエキサイトして暴れまくりながらグリッサンドギターを大爆音でプレイ、いやはやDaevidの斯様なヴァイオレンスなパフォーマンスを観た事がなかった為、少々面喰らってしまった。65歳でこの暴れっぷり、まさに恐るべし。年齢的にDaevidと私は「子連れ狼」の柳生列堂と拝一刀の如きなれば、一刀が老練列堂の前に敗れ去った下りも下せようと云うものか。
Parisで行われたカンタベリー系フェスティバル「Festival Les Toritonales」にも出演したが、こちらはまた全く異なる世界を展開。このフェスティバルは、3週間に渡って夜毎各1ユニットが演奏すると云ったもので、他の日程の出演者を見てみると、Christian Vander Offering、Christian Vanderの娘Julie Vanderが参加しているAD Vitam、同じくMagmaファミリーからFaton/Seffer/Cuasse – Ethnic Trio、元Soft MachineのHugh HopperとElton DeanによるPoly Soft、Richard Sinclair、Phil Miller’s in Cahoots、Pip Pyle’s Bash、そしてJohn Greaves – Roxong Trio、 Mats & Morgan、Guapo他、日本の一部プログレ・ファンの方々なら涙モノの豪華ラインナップであろう。Guru & Zeroは勿論ヨーロッパ初お披露目であり、果たして客は入るのであろうかなんぞと思っておれば、Gongファンは勿論の事、AMTファンも大挙して押し寄せ超満員。
Daevidはコンサート前に「フェスティバル主催者は『ラウンジ・ジャズ的なものを望んでいるらしいので、敢えて我々は爆音でエキサイティングにロックしよう!」と提案。Paris在住のGongのメンバーDidier MalherbeとAMTからは東君をゲストに迎え、2部構成のステージを展開。この日もDaevidは爆音でグリッサンドギターを奏でるが、私の弓弾きによるギタードローンとのアンサンブルが、何ともトリッピーな世界を展開。2セットを終了し更にアンコールにも応え、Daevid共々「いいコンサートだった」と楽屋へ戻るや、主催者側から「客がアンコールを求めて誰も帰らないから、もう少し演ってくれないか」と催促される。疲れたからと一度は断ったものの、されどアンコールが止まず、主催者側からの再三に渡る執拗な要請もあり、再びステージへ。よくよく見れば、最前列にはAMTとGongのTシャツ姿が犇めき合い、このドラムさえも存在せぬ「Vo x 2 + G x 2 + Syn x 2 + Winds」と云う究極にスペーシーなだけの編成が、何をそこまで熱くさせてしまったのか。何にせよ大盛況にて終了、終演後楽屋では、メンバー、スタッフ、次から次へとやって来るGongファミリーと思わしきヒッピー親爺やピッピー婆軍団が入り交じってのパーティー状態。「主催者側は絶対に我々の音楽を好んでおらぬだろうが、本フェスティバル最高動員数であった為、何も文句が言えぬようだ。痛快、痛快。」とAllen翁ことDaevidは水戸黄門宜しく大笑い。
祭りも終わり、さてDaevidと共に、主催者が用意してくれたホテルへと向かう。「一つ星ホテル(一番の安ホテル)だったりして!」なんぞと冗談を交わしておれば、いやはや本当に一つ星ホテルであった。トイレとシャワーが共同でなかった事がせめてもの救いか。されど中庭には緑が溢れる古いホテルで、質素な部屋もこれはこれで雰囲気はゴダールの映画にでも出てきそうな感じにて、ミーハーにフランス幻想を抱く私なんぞ、すっかりこの雰囲気を満喫。唯一の失敗は、酒の用意をし忘れた為、折角のミーハー気分に少々水を差された事か。
旧友と云えば、今回も多くのミュージシャン友達と再会を果たした。
先ずはSan FranciscoにてMason Jones、彼こそが日本のアンダーグラウンド・ミュージックをアメリカに紹介したキーパーソンである事は周知の事実。もし彼とジョン・ゾーンが居らねば、日本のこの手の音楽がアメリカにて注目される事は、もっと後になったであろう。Masonもギタリストであり、自身のグループ「SubArachnoid Space」と云う何とも覚えにくい名前のドローン系ミニマル・サイケグループを率いていたが、先日円満脱退した模様。どうやら今後はソロやセッション活動を展開するそうな。(今年の6月末に日本でも数公演を行っている。)このSubArachnoid Spaceは、ほぼ会う度にメンバーチェンジを繰り返しており、今回もMasonのみならず新ベーシストであったStooまで脱退した模様。今や実質的リーダーであり唯一のオリジナルメンバーである女性ギタリストMelynda Jacksonの性格のキツさに閉口するのかどうかは、我々外野の知る処ではないが、察するにきっとそうであろう、否、そうに違いない。されどそのMelynda、実は結構可愛らしい女性っぽい側面を持っておれど、何せ妬み深く文句垂れである事が玉に傷と云った塩梅か。バンド内で彼女と唯一対等であったMasonを失ったこのバンド、今回紹介されたMasonに代わる若い新ギタリストも既に完全にMelyndaの尻に敷かれている有様なれば、一体今後如何な具合に迷走するのやら。
Chicagoでは、昨年初来日を果たしたPlastic Crime WaveことSteve Kracowと再会。「Galactic Zoo」と云うマニア間では有名なサイケ雑誌の編集出版を手掛ける彼は、最近レーベルをも設立。自身のグループ「Prastic Crime Wave Sound」を始め、我々の呼ぶ処の「Chicago阿呆サイケ・シーン」のグループを挙ってリリースしていく様子。そんな中、Acid Mothers Templeの新しいライヴLPもリリースされると云う事で、我々も「阿呆サイケ」の一派と云う事になろうか。彼が以前率いていた「驚愕の気狂いサイコ(サイケにあらず)トリオ」である「Unshown」の気狂い女性ドラマーTera Pet率いる新たなギャルバン「Spires That In The Sunset Rise」とも今回共演したが、これは本当に素晴らしかった。The ShaggsかThe Fugsかと云う出鱈目な雰囲気の中、されど暗黒チェンバー系をミックスしたようなComusとでも云えば想像に易いか。あまりの衝撃で、思わず彼女らの1stCDRとTeraの1stソロCDRをゲット。天才と気狂いは紙一重と云うが、まさしく彼女は気狂いであり多分天才であろうか。そのTeraは現在身重で、腹ボテ姿でチェロを弾き絶唱する姿は鬼気迫るものがあった。
Philadelphiaでは最近Mogwaiとツアーを行っているアメリカインディー界の重鎮「Bardo Pond」の面々と再会。初めて会った時より大ファンである美形女性ヴォーカリストIsobelも、随分年齢を重ねたせいか、顔付や舌っ足らずな喋り口調は変わらねど、下腹はアメリカ人らしく異様に膨れつつあるのを知るや、思わず見て見ぬふり。私にとって「アメリカ女性最後の希望」であった彼女の変容には、流石にショックを隠し切れぬ。されど自分もまた密かに同じ道を辿っておれば、他人を叱責する事なんぞ出来よう筈もなし。況してや彼女が可愛く優しい女性である事は今も変わらぬのであるから、これしきの事は大いに目を瞑れてしまう辺り、流石「Mr.Cash(現金男)」の異名を持つ私である。
今回のツアー最終地であるSeattleには、Kinskiが我々を待ち受けていた。彼等は丁度我々がイギリスをツアーしていた頃、日本公演を行っていた。今回の彼等の日本ツアーは、前回私が招聘した時とは大きく異なり、連日連夜に渡る馬鹿騒ぎもなく、少々寂しかった様子。「次回はまたAMTと日本ツアーを」との申し出、快く引き受ける。Kinskiは私の勧めもあり、現在Sub Popからリリースを重ねているが、次作はAMTとのカップリングCDになる予定。と云う訳でKinskiのリーダーChrisに連れられSub Popの事務所を訪ねれば、いやはや流石に立派な事務所にして、スタッフ各自が各々自室を宛行われ、どの机にもiMacが設置されていると云う、まさしく立派な「オフィス」である。各々部署も明確に分かれており、インディーとは云え、アメリカのデカいレーベルとは、斯くも立派なものなのかと改めて驚嘆。我がAMTなんぞ、倉庫とは我が家の風呂場と洗面台を繋ぐ廊下であり、オフィスとは私の部屋の一角に設置されている木製机を指す有様である。「いつの日か我々も…」と、レーベル共同経営者である東君と固く誓い合った…筈もなし。
さてKinskiはアメリカインディー界を代表する酒豪バンドである。そしていつも我々の為に、冷蔵庫いっぱいにビールを冷やしておいてくれている。これを空けて帰らずして何がAMTぞ。ここSeattleはツアー最終地なれば、我々一同この1ヶ月間に渡る連日連夜の暴飲ぶりにてすっかり胃こそ焼けておれど、ここで飲まねば日本男児の名が廃るとばかり、Chrisとは例によって明け方まで飲み明かす。
何にせよ、普段滅多に会う事が叶わぬ友人達との再会は、心身共に厳しいツアーに於いて、ひとときのオアシスの如きもの。
よく「日本とこっち(外国)とは違うか?」的な質問を戴くが、私にしてみれば、社会背景や文化、価値観等、勿論異なる点は多かれど、詰まるところは「自然があり街があり人がいる」と云う点で何処であろうと同じである。(そう云えば外国人は直ぐに「君の住んでいる街の人口は何人だ?」「東京の全人口は何人だ?」と云う類いの質問をして来るが、私なんぞいちいち人口数なんぞ覚えておらぬし、日本人から斯様な質問の類いを受けた事もないが、何故に人口数なんぞ気になるのであろうか。人口の多さだけでは、その街の大きさは到底図り切れぬだろうて。)何処へ行けども社会があり人がいる限り、つまらん人間もおれば鬱陶しい輩もおるし、一方で気の合う人間もいる。17年間も住居を構えている名古屋には然程友人は殆どおらねども、片や海を渡った遥か彼方には多くの友人がおり、彼等と再会する事、そしてまた新たな人々とも出会うと云う事は、私の人生に於いて長らく「諦めていた」夢のひとつであったが故、本当に嬉しい事この上なし。考えてみれば、この世には数十億と云う人間が存在しながら、自分の一生で出会える人間なんぞ極々微々たるもの。旅に明け暮れる我が人生なればこそ、「一期一会」なる言葉が妙に身に沁みる年齢になったと云う事か。
(2003/7/5)