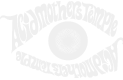Acid Mothers GongのJapan tourも恙無くとは云えぬにしろ、何とか無事終了し、J.F.Pauvrosとのヨーロッパ・ツアー、AMT@All Tomorrow’s Party UKと、足掛け1ヶ月に及んだ怒濤の多忙期もひとまず幕。
Daevid Allenの来日が遅れた事により、多くの方々に御迷惑をお掛けしました事、遅ればせながら、今一度この場を借りてお詫び申し上げます。
幸いにもClear Spotの奥成さんの計らいにて、ツアー最終日に急遽Bridgeにて「振替公演」が行えた事が唯一の救い。この度は一切のプロモーターを介さず、Daevid、Gilli、Joshの航空券やホテル代は勿論の事、全ての経費をライヴのギャラから捻出する事を前提に、 全て自分達の手によってこのツアーをオルガナイズしたのだが、興行的に失敗すれば大赤字を抱える事は勿論覚悟の上であったにせよ、Daevid不在によるキャンセル等で会場側から違約料なんぞ請求されておれば、今頃斯様に悠長にはしておれなかった筈で、迂闊にClub Quatro辺りを押さえなくて良かったと痛感。Daevid不在に加えて、残念ながらDidierも病欠とあれば、Gilliひとりに「Gong」の看板を背負わせて初日からの3日間ライヴを行ったが、然程の問題もなく終わり、漸く3日遅れで到着したDaevidを、関西空港にて無事ピックアップした際の私の安堵感と云えば、それは到底言葉にならぬ程。
ここで改めて云うまでもないが、「Acid Mothers Gong」とは、名前の通りGongとAcid Mothers Templeの合体ユニットであるが、単なる企画モノのユニットではなく、歴としたバンドとして位置付けられている。現在「Gong」の名を正統継承しているユニットは、昨年Daevidにより結成された「youNgong(改め『Gong』)」であり、かつて「Gong」の名称を冠していた「Classical Gong」は、Daevidの意向により既に消滅したようで、Daevid曰く「Classical Gongは悪夢」らしく、「コピーロボットに演奏させたい」やら「『Camembert Electrique』のTシャツを着たヒッピー親爺共が最前列に陣取っているのを見るだけでうんざりする」等と、常に変化を追究して来たDaevidにしてみれば、それも当然の顛末なのかもしれぬ。
昨秋ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールにて行われた「Acid Mothers Gong」初公演は、本来「Gong (ex. youNgong)」として行う予定であったが、DaevidとGilliの息子でありドラマーでもあるOrlandoと、彼の相棒であるベーシストDharmaの解雇以降、リズム隊が見つからぬと云う非常事態から、急遽「Acid Mothers Gong」として行う事となった次第。当初は昔のGongの曲を演奏するアイデアもあったが、Daevidの発案により、結局全編インプロによる90分間の大爆音コズミック・セッションとなり、全員でただ踊り狂う阿呆なパフォーマンスさえも披露、まるで「気違いヒッピーの祝祭」の如きで、一部の狂信的オールドGongファン(と云った処で「3部作」辺りのファンであろうが)からは「Gongは終わった…」と批難業々、されど一方で「これこそ本来のGongの姿」と熱い支持も受け、Daevidはこの両方の反応をいたく喜んでいた。またDaevidは、津山篤+吉田達也によるリズム隊を「Gong史上最強のリズムセクション」と絶賛、そして「Acid Mothers Gong」は単なる合体ユニットから、ひとつの新たなGongとして位置付けられる事となり、彼からの再演の希望により、今回のJapan tourをオルガナイズする下りとなったのである。
昨年2月にオーストラリアにて録音されたGong(録音当時の名称は「youNgong」)の新譜「Acid Motherhood」は、DaevidとGilliによる「Gongの変革と蘇生」がテーマとなっていた。「Gong史上初めてサックスが入っていないアルバム」等と云う表層的な事のみではなく、ロイヤル・フェスティバル・ホールに於けるパフォーマンス同様、旧態依然としたオールドGongファンに対するDaevidとGilliからの回答となっていると思われる。録音作業上に於ける諸問題はいろいろあったにせよ、オーストラリアでの録音時には、精々「ネタ」的なものしか録音出来なかった事を思えば、最終的にDaevidが全てをプロデュースし完成させた経緯を持つこのアルバム、彼のこの1枚に賭ける意気込みは、相当だったと伺い知れる。ジャケットも従来のGongのそれとは全く毛色の異なるもので、Daevidよりメールにて、表ジャケットのデザインが送られて来た時には、流石に言葉を失ったものである。(裏ジャケットに自分のあんな写真が掲載されているとは、この時は未だ知る由もなし。)Daevidは、ジャケットのコンセプトにさえ「Gongの変革」を掲げ、「多分一部のGongファンは忌み嫌うだろうし、しかし一部の人達は受け入れてくれるだろう」と、当初より賛否両論に分かれる事を前提に考えていた様子。「Gongは本来持っていたエネルギーをすっかり失ってしまった。だからそれを再び取り戻さなければならない。」彼自身が「アナーキストだった」と云う本来の「Gong」の定義と、一般に思われている「ファンタジックな宇宙ヒッピーサイケバンド」としての「Gong」のイメージとは、今や大きくずれてしまっている事は明白にして、しかし結成30年を越えた今、何故彼はそこまで「Gong」にこだわるのか。
Daevidの音楽に対する真剣さは、あのステージに於ける阿呆なパフォーマンスの表層からは、到底伺い知れぬやもしれぬが、故に果てしなくメンバーチェンジを繰り返す羽目となり、また一方で様々なユニットを結成しては、思いつく事を片っ端から演ってみるのであろう。完全主義者のようでありながら、実は必ずしもそうではなく、実際リーダーでありながら、本人はリーダーにはなりたくないと云う。よくよく考えてみれば何と自分と似ている事か。私も自身のグループを幾度となく結成しては、メンバーチェンジを繰り返し、実際リーダーにして音楽的にも主導権を握りながら、矢張りリーダーではありたくないと思うのである。これはFrank Zappaの如き孤高の完全主義者でもなく、Robert Frippの如く詭弁にて自己弁護し得る訳でもなく、Jerry Garciaの如く当初より素晴らしいメンバーに恵まれた訳でもない、何とも不器用な生き方を選んだ者の哀しみか。
結果、矢張り自分の理想に対して自らの限界を知る事となり、他力本願的に他のメンバーの才能に頼らざるを得ぬ訳であるが、それが彼にとって、かつてはSteve HillageやPierre Moerlenであり、またPlanet Gongに於けるHere & Nowであり、New York Gongに於けるBill Laswellであり、今回はたまたま私でありAMTであっただけなのであろうと思う。そもそも「Gong」とは果たして世間一般に云う「バンド」であったのかさえ、私にとっては疑問であり、面白いミュージシャンがいれば合体して行く、まさしく「共同体」的なものではなかったか。それはメンバーチェンジに泣かされ続けた私が「正式メンバーを決定しない」と云う苦肉の策のコンセプトの下に結成したAMTと、ある意味近いのではなかろうか。
今回のAcid Mothers Gongの全公演は、完全なるインプロであり、セットリストも存在せねば事前の打ち合わせも皆無にして、ステージ上にてメンバー各々の思惑が交錯する展開となった。「Flying Tea Pot」等のClasical Gongのスタンダードとも云える曲でさえ、私が勝手にリフを弾き始めた事に起因するのみにして、果たしてDaevidが同調して歌うかどうかなんぞ、私の知る処ではなかったし、結果的に東京と大阪の2公演でDaevidは歌っていたが、これも果たして彼自身の本意だったかどうかは、今もって私の知る処にあらず。されどDaevidは、少なくともAcid Mothers Gongに於いては、完全にインプロで演奏する事を念頭に置いており、結局それが「Gongの変革と蘇生」についての糸口となっているように思える。今回の演奏について、一部で「Gong本来のスピリットが欠けている」等と酷評されているそうだが、そもそもその御仁等は一体何を期待しておられたのか。それこそDaevidの云う処の「『Camembert Electrique』のTシャツを着たヒッピー親爺共」と同じな訳で、結局はDaevidやGilliの思う処の何も理解されておらぬどころか、そもそも何の為に御丁寧にも「Acid Mothers Gong」と名乗っているのか、と云う事であろう。先頃ダモ鈴木氏と名古屋公演にて共演した際も、どうやら「CAN」を期待して来られた一部の御仁等に「今年のワーストライヴ(2月にも関わらず何と気の早い事!)」と酷評されたらしいが、そんなもん期待するんやったら家で「Tago Mago」でも爆音で聴いてたらええねん。今現在のダモ鈴木氏が共演者に期待しているのは「CAN」の幻影ではないし、それが判っていたからこそ韓国公演の楽屋にて、ダモ鈴木氏に「名古屋では『CAN』のような演奏は絶対しませんから」と宣言し、「それはとても楽しみですね」とのお言葉も頂いたのである。お金を払って観に来て頂いている限り、当然我々も楽しんで頂こうと真剣に演奏している訳であるが、そもそも求めているものが異なる御仁に対してまではその限りではない。INU再結成(実際は「FUNA」であったが)の際、そのあまりの音楽性の違いに腹を立てた客(私の友人)に対する町田町蔵の言葉を借りれば「そりゃ兄ィちゃん、八百屋に来て魚くれ云うようなもんやんけ。」
何にせよ全公演盛況にて終了、DaevidとGilliを関西空港へ、東京観光したいと云うJoshを新大阪駅へ送り届けた今、先のヨーロッパ・ツアーに於いて痛めた肋骨の治療に専念したい処だが、1ヶ月後から始まるAMT USツアーに向けた準備やら、何としても完成させねばならぬAMTの新譜の数々、到底それどころではなし。最終日Bridgeにての振替公演後に訪れたスパワールドにて、のんびり露天風呂に浸かれたのが唯一の救いか。今年も残す処7ヶ月半であるが、5月中旬~6月中旬までの1ヶ月間はAMTのUS tour、7月下旬から8月中旬まではKinskiにギタリストとして参加しUSツアー、8月中旬から2週間はMaquiladoraの来日公演に同行、9月初旬から10月中旬まではGongの欧州ツアー、10月下旬から11月末まではAMTの欧州ツアーと、もう年末まで休みが取れぬ事は承知済み。しかし流石に疲れたなあ。一体いつになればのんびり出来るのやら…。Daevidのように精力的に活動しつつも「ゆるい」時間を大切にしているライフスタイルが羨ましくもあり、斯様な事を思うとは、いよいよ我も老いたか。齢66歳にしてあのテンションのDaevidや、直ぐにまたスペインへツアーすると云っていたGilli(何と彼女は数年前に9ヶ月間の長期ツアーに出ていたとか!)、あの二人のエネルギー源はオーストラリアの大自然だと語っていたが、ならば私も何処か海の見える場所にでも引っ越したいものなれど、先立つものもなければ、結局当面は突っ走り続けるしかなかろうか。
それにしてもDaevidとGilliの醸し出す空気感、何とも荒唐無稽にして無為自然な事か。歳を重ねるならば、せめてあの様に大らかでありたいもの。「サイケとは何か?」このよく尋ねられる問いの答の片鱗を、今回のツアーで彼等から垣間見た気がする。
ツアー終了後に、Joshを奈良観光に案内した際、法隆寺の百済観音像を見てふと思う。「百済観音ってDaevidに似てるなあ」鼻筋が長く優しい目元、仏像にしては珍しい八頭身の長身、そして何よりその「さりげない」立ち姿こそ、これぞまさしく彼の云う「Open」ではなかったか。
<おまけ>
昨年2月にオーストラリアで行われたGongの新譜「Acid Motherhood」のレコーディング日記を見つけたので、ここに「おまけ」として追加しておく。ステージ以外でのDaevidの人間像が、多少は判って頂けるやもしれぬ。興味ある方はここを![]() クリック。
クリック。
(2004/4/16)