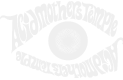今回は、私が個人的にこよなく愛して止まぬ「オクシタン・トラッド」のアルバムの中から、変わり種を1枚紹介。所持するオクシタン・トラッドのほとんどは、ヨーロッパ・ツアーの際、Toulouseなどのレコード店やフリーマーケットなどで見つけたもので、詳しいアルバム/ミュージシャンに関する情報は、はっきり言って不明。私はマニアでないし、なにしろオック語は全く判らないし、仏語もほんの片言。
-CANTS DELS TROBADORS/Regrelh [ventadorn 1979:LP]
Toulouseのフリーマーケットにて、ventadornは「オクシタン・トラッドを出しているレーベル」という理由のみで購入。Regrelhなるこのグループについて、当然何の知識もなし。ライナーノーツに「これこそが20世紀のトルバドールだ」と書かれているが、この手のフレーズこそ、70年代以降の売れないトラッド・バンドに押される烙印。
A面は、オック語によるオーソドックスな独唱で幕を開ける。トラッド・バンドにしては珍しいぐらいの敬虔な佇まい。この空気感は、素朴なトルバドールを奏でる同じオクシタンのデュオ「FIN’AMOR」より深みがある。しかしいきなり2曲目は、ピエール・アンリばりの前衛的電子音ソロが爆裂。と言うのも5人編成の内2人が「シンセサイザー」「音響技士(tecnica del son)」のクレジットで納得。これがあのキャッチコピーの所以か?このどこか田舎臭い洗練されていない電子音は、最近の音響派とは全く別次元のもの。しかしこの田舎臭さは、まさしくあの時間が止まったままのオクシタンの景色に、何故かフラッシュバックする。その電子音ソロにviela d’arquetがクロスフェードして幕を開ける3曲目。 フェイザー全開のelectric guitarにbassとpercussionも加わって、Ash Ra Tempelの様な疾走感のあるトリップサウンドへ展開。まるでB級ジャーマン・ロックの香り。あの南仏の気候や自然からは全く結びつかぬサウンド。間違えても、あのオクシタン・ダンスは踊れないし、フランスならではの男と女の世界もここには無い。残った電子音のドローンにようやく歌が重なる4曲目。ここでのドローンは、viela a roue 的役割を担っているのであろう。故に歌とドローンの違和感はほとんど無いようにも思えるが、このスぺーシーな感じこそがまさしく20世紀のトルバドールなのか?20世紀とはそれほど安易なものだったのか。更にメドレーで、強烈にチープなfuzz guitarを中心に、左右に飛びまくる電子音とviela a roueの代わりのドローン、 viela d’arquetとpercussionとのアンサンブルで 中世の器楽曲が展開されるが、唐突にエコー音のみを残しブツ切れで終わる。
B面はいきなり電子音のドローンから幕開け。その上にオック語での朗読が朗々とつづき、遂に宇宙音まで登場する、まるでアシッドテスト。つづいて、ようやく電子音も消え、viela d’arquetのみをバックに歌われる。更に独唱へとつづく。この辺りの佇まいは、音楽的に卓越した高度な技術は感じないが、所謂いかにも伝承音楽と言った香りのする敬虔な中世の世界。本来、個人的にはこの感じはたまらなく好きなのだが。しかし最後は、朗読と再び電子音。それも初期のクラウス・シュルツのようなサウンドにcornemuseのような音まで重ねた、暗黒電子音バグパイプ重奏とでも表現すれば想像できるか?
1979年にもなって、 何故トルバドールと電子音なのか?これが「20世紀のトルバドール」と言う事なのだろうか。単に時代遅れの田舎音楽家だったのか?この地区ならではの突然変異だったのか?それとも単なるアホだったのか?かく言う私も79年当時、シュトックハウゼンなどに影響を受け、奈良の田舎で電子音を使った作品ばかり作っては、一切誰にも相手にされていなかった。果たして彼等は今、どうしているのか?
(2001/3/17)