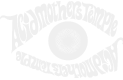5月下旬から、今年もソロでイタリアとフランスをツアーする。否、正確にはフランスは、仏ギタリストJ.F.PAUVROSとのデュオ・ツアーである。私は彼と以前にギターデュオで1枚のアルバムをリリースしているが、この190cmの長身ギタリストについては、来日して灰野敬二氏や吉田達也氏とライヴを行った事もある故、御存知の方もいらっしゃるだろう。
初めて彼と出会ったのは、1999年の事であった。
99年5月AMTのツアーに於いて、イギリスからノルウェーへ渡るフェリーの都合がつかず、結局ノルウェーの全日程をキャンセルせざるを得ず、仕方がないので宿を求めてパリの友人宅を訊ねた折、「フランスのギタリストが君とセッション録音したがっている」と云う話が舞込み、丁度ヨーロッパをひと回りして再びパリに戻ってくる上、数日パリでオフを過ごす予定だった為、その申し出を快諾したのだが、その後ツアーの最中に私はフランス女性と恋に陥ち、結局そのオフを彼女と共に過ごした為、このセッションの約束を軽くブッちぎってしまったのだった。再びメンバーと合流する為、彼女に後ろ髪を引かれつつもパリへ戻った私に、そのセッションの仲介者は「enjoy your life」と、私の身勝手に怒る事もなく、またそのギタリストも私の愚行に対し、寛大な「では次回こそ」と云うメッセージを残してくれていた。
さて同99年11月、私はソロで再びフランスを訪れる事となった。途中、同時期にフランスをツアーしていた「Japanese New Music Festival」のRuins+津山さん御一行と合流し、「聖家族」のライヴをやったり、Ruinsに津山さんと共に参加して、4人で「Hyderomastgroningem」を演奏したりした後、フランスの彼女の住む街にて彼等と別れ、丁度その後のスペインでのソロツアーがキャンセルになった為、その2週間を彼女の家で過ごしていた。そこへ前回セッションの仲介をしてくれた人物から連絡があり、このソロツアー最終日に予定されているパリでのフェスティバルにデュオで演奏出来ないかと、そのギタリストが打診してきたと云う。更にその前日にスタジオでセッション録音したいとの話も出ていた。前回恋にうつつを抜かし不義理した手前、勿論その申し出を快諾した事は言う迄もない。
さてパリのスタジオで初めて見るその長身のギタリストこそが、J.F.PAUVROSであった。彼に対して全く予備知識のなかった私は、取り敢えず話すより音を出す事を選んだのだが、演奏を始めていやはや本当に驚いた。何と使うギターからエフェクター、音作りまで酷似している上、ギターの弓弾きと云う手法まで同じなのである。彼も「ギターを始めて二十数年経つが、自分以外に弓弾きするギタリストを見たのは初めてだ」と驚いていた。セッションを進めていくうちに、どうやら「即興演奏」と云うものに対する考え方まで酷似していることが発覚。お互いまるで「自分が2人で演奏しているようだ」とまで錯覚する始末で、時間を忘れて演奏を楽しんだ。
セッション録音終了後、スタッフ達と共に我々はレストランへ出向いたのだが、そこでこの日の我々のファースト・ミーティングについて彼は、「70年代初頭に大人数のギターアンサンブル(フランス版グレン・ブランカのようなものらしい)に参加していたが、その時の事が彷佛された」と語り始めた。何でも私のギターの音が、20人ぐらいのギターアンサンブルのようであった為とか。そしてお互いに共通した感想は「通常、即興で演奏する場合、回数を重ねる度に退屈なものに成り下がってしまうのであるが、このデュオの場合、まるで作曲/編曲/演奏を同時に行うと云ったプロセスを辿る為、回数を重ねれば重ねる程、完成度が上がっていくだろう」と云うものだった。これこそ私が常日頃から思う「真の即興演奏」と云うものであり、俗に云う「インプロ」だの「フリーミュージック」だの「インタープレイ」だのの「退屈極まりない」ダラダラとした「音の垂れ流し」こそ、私の最も嫌うものである。私は13歳で音楽を始めた当初から、四半世紀に渡りこの手法の下で演奏してきた訳で、それはMUSICA TRANSONICで更に昇華され、またAMTの録音さえもこの手法でベーシックが作られている。実はこの手法について、言葉では理解していても、実際に音を出すと全然ダメなミュージシャンが多い中、またひとり此処に「真のミュージシャン」と出会えた事が、私には大層な喜びであった。
翌日のフェスティバルでの演奏は、終盤で突如私のトランス(変圧器)が壊れ、殆どのエフェクターが使用不可となって苦戦した事を除けば、前日のセッションより良い演奏であった事は言うまでもない。そして我々は再会を誓ったのだが、その後お互いあまりに多忙を極め、結局今回のツアーまで顔を合わせる事さえ出来なかった次第。
さて久々の再会にして、一体如何な世界が広がっていくか、今からとても楽しみである。
私は、バンドも好きだがソロも好きで、これら両方とも不可欠にして、これでバランスを保っている処があるのだが、一方でコラボレーションも音楽活動をしていく中でのひとつの愉しみに違いない。
最近ではRICHARD YOUNGSとのコラボレーションが、正に自分としてはやり甲斐のある仕事にして、お互い「美しい音楽」を目指している事で共通する。最近の彼の作品は、ボーカルをフューチャ-したシンプルなものが多く、最新作「MAY」も素晴らしい作品であった。
今回のソロツアーの最後は、Frederic率いるUEHとの共演で、且つスタジオにてセッション録音もする予定であるが、このバンドも私の愛するバンドのひとつで、彼等と演奏する度、その純粋な魂に心洗われる想いである。
またSan DiegoのバンドMAQUILADORAとも、今年の夏にコラボレーション作品を作る予定である。先のAMTのツアーに於いて、前座を務めてくれた彼等のライヴに思わず落涙。音楽で泣かされる等、それもディープ・パープル再結成ライヴに於いて、あまりのノスタルジーから落涙したのとは全く異なり、本当にその音楽に感動して涙する等思ってもみぬ事で、そんな彼等とコラボレーション出来る機会が持てる事自体、嬉しさ余りある。 名古屋のフォークユニット正午なりとのコラボレーションも随分長きに渡るが、「うた」と即興にて絡む事程ギタリスト冥利に尽きる事はない。やはり音楽は「はじめにうたありき」である。
「うた」と云えば、四国に引き蘢ってしまって久しい井内賢吾氏とのコラボレーションこそ、私にとっては「うた」とのコラボレーションと云う事に於いて、まさしく真骨頂であったやもしれぬ。彼は、私と演奏し始めた頃から、自身のパブリックイメージを破棄したがっており、故に毎回、彼の真の肉声と対峙する壮絶な演奏となった。東京での活動に疲れ果てて彼が音楽活動を止めてしまった事は、彼の本当の「うた」が開眼する直前であった事もあり、非常に惜しまれる。
ギター同士と云う点では、宮本尚晃氏とのデュオは、J.F.PAUVROSの時とは全く異なり、彼の美しくも儚い孤高のフィードバックに対し如何に色づけするか、同じギターでありながら極北に位置する彼の音は、私にとってあまりにストイック且つ厳しい音で、何物にも混じらぬ彼の音と対峙する瞬間、煩悩に塗れた自分の生きざまの如く、自分のギターの背負う哀しさを垣間見る。されどそれこそが我が生きざまなれば、我が奥義をもって応えねばならぬ。そしてこの若いギタリストにこそ、一体自分にとってギターとは何ぞや、と考えさせられてしまうのである。
山崎マゾ氏のSpace Machineとのコラボレーションは、果てしなき「宇宙音楽」の追究と云う意味で、「宇宙音歴24年」の私としてはとても興味深い。単に電子音楽を追究する輩は多かれど、「宇宙音楽」を追究している輩はそうそうお目にかかれぬ。これ程具体的なテーマを持ちながら、さて本当の意味で「宇宙の音」とは何ぞや。音における具体性とは、これこそロマン派以降のコンセプトであり、されど実は誰も聞いた事がない「本当の宇宙の音」とは。しかし誰もがその「宇宙度」を判定出来るのは何故だ。
そして一方、抽象的な意味で「真の宇宙」を感じられるカン・テ-ファン氏とのセッションも、私にとっては素晴らしい瞬間である。やはりその哲学と経験に裏付けられる音は、私の魂を揺さぶらぬ筈がない。
その他、7月には久々に吉田達也氏とのデュオも予定されている。さて今回は一体何が起こるのか。
コラボレーションと云う、決して「音と音の決闘」ではない、共に美しい音を紡ぎ上げる作業は、私にとって興味は尽きず、機会がある限り挑戦していきたいもののひとつである。
さて今後どうせなら、是非とも女性とコラボレーションを行ってみたいものだ。さりとて女性にとって私の印象がどうにも芳しくないのか、全く斯様な機会に恵まれず、この際なので公募でもしてみるか。交歓の果ての「ベッドルーム・セッション」なんぞ是非とも試みてみたいものなれど、斯様な事をホザいているが故、敬遠され機会を持てぬのであろう。しかし「愛の交歓」こそが究極のコラボレーションではなかろうか。ならば矢張りギターは要らぬか。
(2002/4/25)