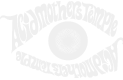先日、姫路マッシュルーム内のぱらぺる堂で、エロ劇画の単行本をまとめて4冊購入。
特に一色一の「けもの獄-牝獣が泣く(東京三世社)」は掘り出し物だ。70年代中期のエロ劇画が放つ、特有の饐えた異臭が充満したアングラな世界。東映のB級ピンク映画と同じ香りである。篠原とおるの「さそり」より、更にドブな世界で、こちらの方が映画版「女囚さそり」に近いと言える。
偶然にもその数日前、まるでガルシアの如き親爺が鎮座する近所の古本屋「オリオン書店」にて、あの滝沢解と川崎三枝子のコンビによるエロ劇画の大名作「黒衣の女」の単行本(双葉社)を100円で購入。この値段は昨今のエロ劇画ブームの風が吹き荒れる中、奇跡としか言い様がない。この作品は、エロ劇画と位置付けられてはいるが、内容は決してエロではない。ましてふくしま政美と数々の衝撃作を発表した滝沢解である。ふくしまの筋骨隆々とした肉弾劇画とは異なり、女性らしい繊細な画風の川崎三枝子とのコンビでは、女性心理に潜む悪魔的な側面を馬鹿馬鹿しい程ストレートに描いている。そして、こういった女性の悪魔的側面にこそ魅了されてしまうのもまた、男の哀しい性なのか。
70年代から80年代初頭にかけてのエロ劇画なるものに漂う、エロ云々以前の人間臭さに、私はどうしてもロマンを感じてしまうのだ。
私とエロ劇画との出会いは、今を遡る事30年弱か。6歳の時に永井豪の描く「ボインの女の子」の洗礼を受けて以来、私の中で何かが目覚めてしまった。それまで怪獣に夢中だった私は、突如「裸の女の子」にのめり込んで行った。と言っても、単に今まで怪獣の絵しか描かなかったのが、ある日を境にボインしか描かなくなったというだけであるが。いや正確には、当時怪獣の代わりに仏像にもハマっており、仏像とボイン(時にはそれらが融合されていた)ばかり描いていた、と言うのが正しいか。
元々無類の漫画好きであった私は、ほぼ毎日、近所の本屋で週刊誌やら単行本やらの立ち読みに明け暮れていたのだが、ある日、とうとう読むものが無くなり、その時気付いたのがエロ週刊誌の存在であった。そこには私が求めてやまぬボインが、極楽浄土の無限の花園の如く、ページ狭しと咲き乱れていた。しかし子供ながらも一人前に羞恥心は備えていたようで、あまり堂々と見る訳にはいかぬと感じ、夕方の社会人が帰宅途中に本屋に立ち寄る時間を狙い、エロ週刊誌を立ち読みする親爺共と肩を並べる事にした。「お前かて読んでんねから、俺かて構へんやろ」と云う一種の共犯心理である。斯様にして私は堂々とエロ劇画を読む免状を、自らに下したのだった。
当時は性描写の意味する処さえ全く理解出来なかったが、兎に角そんな些少事は大して気にも留めず、ただひたすら少年漫画で目にするものより、より肉感的なボインに目を血走らせていた。しかしたかがボインである。暫くするとボインよりも、エロ劇画に漂う饐えた人間臭い雰囲気に興味は移っていった。単にボインが見たいのであれば、矢鱈と衣服を剥ぎ取られて尚、恥ずかしさで涙を浮かべつつも笑っている永井豪の描く女の子の方が、当時まだ性体験の無かった私にはシビれるものがあった。
また当時から私は、東映等の邦画が持つ薄暗く貧相な画面が好きで、どうしてもハリウッド映画の持つ華やかさには抵抗があった。そんな事も起因してか、エロ劇画のディープな世界に何の抵抗も無く滑り込んで行った。
およそエロ劇画の顛末とは、男の情けなさに思わず苦笑する反面、女の業の深さに背筋が寒くなるパターンが今も変わらず主流だ。うだつの上がらぬエロ劇画を読む事でしか救われないような読者が羨む、あまりに出来過ぎたお膳立てでの美女との情事には、必ず何かしらのツケを払わされるオチがつき、つまるところ読者は「美味しい話には裏がある」的な心理から、単に傍観者としてエロ劇画を愉しみ、そして自己完結出来るような構造になっている。故にエロ劇画の読者が、女性問題にまつわる凶悪犯罪等に手を染める事等あり得ないのではなかろうか。女性との人間関係に対する夢想的な希望的観測を持たせない、嗚呼、何と人生に於ける真理なのであろうか。極論を言えば、これはもう仏教で言う「無常」であろう。
私がエロ劇画から学んだ事は、人生に於いて「何も期待しない」という事だ。全ては「なるがまま」であり、むやみに期待するという行為は、必要以上に失望させられるという事と同義である。何も期待していなければ、どんな些細な事であれ感動出来るというもので、その方がよほど人生楽しいではないか。エロ劇画には、男の悲しい宿命が描き綴られており、暴走しがちな少年達にこそ読ませねばならぬ。
子供の頃流行った笑福亭鶴光が歌うピンクレディのSOSに対するアンサーソングに、こんな一節があった。
「狼なんかじゃありません/男は悲しいいきものよ/騙したつもりが騙されて/(中略)/今日もまた誰か世間のさらし者(若しくは笑い者)」
最後に私がお薦めするエロ劇画を2点。
「変態教室/紺野泰介」サン出版
これは80年代の作品。84年頃は、どこの古本屋に行ってもエロ劇画コーナーに必ずあると行ってもいい程よく見かけたが、最近はめっきりお目にかからなくなった。東大受験を控える息子の性的欲求解消の為、オナペットになってやる母と妹、更には口と肛門まで提供する父親と云った家族挙げての苦労話、生理の女性にしか感じない青年と生理の日にしかオルガスムスを感じない女性の悲話、祖母に仕込まれたが故に醜悪な局部にしか感じない青年と、それを知らず醜悪な局部である事を恥じ逃亡する女性の悲恋話等、人間が各々の性生活に背負う悲しい性が、他には類を見ない鋭角的且つ陰湿なタッチで綴られた 隠れた名作。
「雲母(きらら)/清水おさむ」アリス出版
これは、あの劇画アリスの増刊号「悪徳堕天使」の為の書き下ろし。同時掲載されているのは、あの「アニマル・カンパニー/吾妻ひでお」と暗黒劇画の新鋭「東京パンク/加藤カズオ」で、これらも充分素晴らしい内容である。しかし100頁に及ぶタイトル作には、やはり遥か及びもつかぬ。
清水おさむと言えば、戦国時代から現代を舞台に神と悪魔の戦いを壮大に描いた代表作「アリス伝」のアナーキーな印象があるが、 やはり本作もストーリーは全く破綻している。どうやら宇宙から来た敵対する美男美女を中心にした、エロとヴァイオレンス渦巻くSF大作の様相だが、「きらら」なる女の方が人間と性交渉するうちに人間味を帯び、それに腹を立てた男が人間を滅亡させる為、女共々、関ヶ原の合戦にタイムスリップし、その後の歴史を大きく変え、挙げ句の果てには第5次世界大戦で人類は滅亡し、更に原始人化し女を襲う事しか考えられなくなった生き残りの人類をも虐殺し、遂には地球をも爆破し、ようやく女を手に入れた男は「帰ろう…わが故郷、はるか宇宙の外まで…。」と女の手を取り何処かへ帰っていく。恋に於ける独占欲や嫉妬も、ここまで壮大になると阿呆らし過ぎて、笑うしかない。
コマ割りも、清水おさむ特有の2頁見開きでの爆発シーンや性描写が展開される為、100頁と云うボリュームにしては、一瞬で読破出来てしまう。しかし煩わしい説明的展開が皆無の為、そのドロドロしたタッチの迫力を満喫出来る。
「男と女の色恋とは、かくも理屈は要らぬもの」と云う事を逆説的に実感させてくれる痛快作。
(2001/9/3)