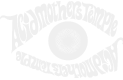先日、東京の某スタジオにてレコーディングせし折、休憩時間にスタジオのロビーにて「おやじロック」なる雑誌を発見、津山さんは既に御存知の様子なれど、普段は週刊アサヒ芸能程度しか雑誌は読まぬ私にすれば、まさに青天の霹靂、そもそも「おやじロック」って何やねん?Deep Purpleの「Made in Japan」について特集されておれど内容はあまりにお粗末、更には「おやじバンドをやる上でのノウハウ」「面白バンドおやじのライフスタイル紹介」等と、余りに下らぬ内容故に思わず失笑、斯様な雑誌を真面目に購読する読者、況してやその購読者層としてシュミレートされる年配諸氏なんぞおるものか。何処をどう読もうが、明らかにRockのRの字も知らぬガキ相手に、大凡我々と同世代の編集者が自虐的ギャグとして、斯様な雑誌を出版せしとしか思えぬ。そもそも「ちょいダメおやじのためのロック・ライフ・スタイルマガジン」って何やねん?
されどネットにてオヤジロックなる語を検索すれば、実に恐ろしきはオヤジロック関連サイトの多さかな。なれば宛らこの雑誌購読者たるも所謂ビートルズ世代なるか。何でもNHK BS2では「熱血オヤジバトル」なる平均年齢40歳以上のバンドを対象とするコンテスト番組が、人気を博しているのだとか。「オヤジロック」と云う一見嘲笑されるやもしれぬその語に敢えて甘んじてまで、オヤジロック・ライフを楽しまんとする斯様な御仁達の大凡にとって、既にロックバンドとは「余暇を昔から好きだったバンド演奏で楽しもう」と云う、趣味のひとつとして、または過ぎ去りし青春を懐かしまんとしての酔狂に過ぎぬのか。まあ誰が如何な趣味を持ち、それが所謂「日曜バンド」の類いであれ、それは各々の勝手にして、かのJerry Garciaも「まずは楽しむ事だ」と、嘗てパルコのCMでも宣いておられれば、別に私が声を荒げて物申す必要なんぞ微塵もなし。なればこの「おやじロック」なる雑誌もまた「園芸入門」やら「鉄道マニア」なんぞと同類の、趣味雑誌の類いに他ならぬか。
昨春に行われしJapanese New Music Festival中国ツアーの際、津山さんと例によって中古レコード屋を探すも、地元オルガナイザー達に、今更中国にはアナログ盤なんぞ存在せぬと諭されし通り、結局1枚のLPさえ発見出来ず終いなれど、それでは収まりつかぬとCD屋巡りに予定変更。CDやDVDの価格が驚異的に安価故、あれこれ悩む津山さんに「どうせタダみたいなもんやねんから全部買いなはれ!」と進言し得る程にして、その津山さんが購入せし1枚にDeep Purpleの新譜「Rapture Of The Deep」あり。このアルバムこそ、一昨年のヨーロッパ・ツアー中に、何処ぞのライヴ会場の壁にこの新譜のポスターが貼られておれば「なんやこれ…Deep Purpleってアルバムか?…ん?ええええええっ!これってDeep Purpleの新譜かいな!なんちゅうダサいジャケやねん…こんなジャケで誰が買うねんな…あかん、終わってるなあ…でもちょっと聴いてみたいな…絶対もうあかんやろけど、俺のIan Gillanへの熱い想いでやっぱり聴いてみたいなあ…でも金出して買うのん嫌やなあ…」と、その時に記憶に留めし1枚なり。ホテルへ戻るや、津山さんは早速携帯用CDプレーヤーにて聴き終えれば、即座に私の部屋を訪れ「ギャハハハハ!あかん!ええとこ1カ所ぐらいあるか思って聴いたけど、曲はまあまあのんもあんねんけどな、でもめっちゃカッコ悪い!何であんなんになってまうねん?Ian Paice何で昔みたいに叩き捲らへんねん?何であんなデジタルの気色悪い録音やねん?こんなん要らんわ!このCDやるわ!」斯くなる下りにて私の手元へ辿り着きしこのアルバムなれど、確かに聴いてみれば「おお~っ!」と思わず興奮せしは、アルバム冒頭に於けるDon Aireyのオルガンによる往年のDeep Purple然とせしおどろおどろしきイントロ数秒のみ。Ian Gillanの声の衰えについては、元々彼の一見ハードなれど実はハートフルな歌こそが好き故に、私個人としては些かの問題もなし。されど確かに全曲ミディアムテンポにして、曲調は何処となくRainbowやWhite Snakeを連想させる辺り、確かに元Rainbowや元White Snakeのメンバーこそおれど、何しろ本家Deep Purpleの名を語りながらも、実はDeep Purpleの派生バンドっぽい音とは、此れ全く本末転倒、されど売れる為にはこれもまた仕方なしか。
そもそも彼等は70年代の全盛期と呼ばれる時代から、常に「新しい音」を築かんと試行錯誤せしは明白にして、されど彼等の音は決して後日に現れるヘビメタなんぞと云う糞の如き代物にあらず、ライヴのMCからも察せられる通り、単にR&BやR&Rを彼等なりにアレンジせんとせしに過ぎぬ。それこそが彼等にとって「新しい音」の探求にして、故にIan Gillanを擁せし黄金期とも云える第2期ですら「シャウトするボーカルに飽きた」と云う、至ってミュージシャン然とせし理由にて(勿論Ritchie BlackmoreとIan Gillanの確執が一因なるも事実)Ian GillanとRoger Gloverを解雇、結局僅か4年間しか存続せず、当時のリリース作品としてはスタジオ盤4枚とライヴ盤2枚を残すのみなり。その後彼等が模索する「新しい音」とは、よりソウルフルかつファンキーな些か黒人音楽然とせしハードロックにして、その結果、音楽的指向の相違から看板ギタリストRitchie Blackmore脱退を誘う下りはあまりに有名。されど残されしメンバーは、新ギタリストTommy Bolinと共に事実上の最終作「Come Taste The Band」を発表、その黒人音楽を見事に昇華せし独自のハードロック・サウンドは、ハードロック史上に残るべき大傑作なれど、Ritchie BlackmoreなくしてはDeep Purpleにあらずと正当に評価されず、結局バンドは解散、何しろ如何せんRitchie Blackmoreが結成せしRainbowこそ、彼の「新しい音」として、Deep PurpleからR&B色を排除し、よりリフ主体の様式美を追究せんとすれば、後日ヘビメタの開祖とも定義付けられ、大いに評価されしは周知の事実なり。より「新しい音」を求めればこそ、その音楽的指向の相違により、全盛期と思えるバンドがメンバーチェンジやら解散するは当然の理なれど、ファンの心理と云うものは異なるものにして「何でこんなんになってもうてん?前の方が絶対カッコ良かったやんけ!」と憤るも無理はなく、況してや主流たるものが、時代によって大きく変遷すればする程「昔の方が良かった」等と云う懐古趣味に走らんとする風潮も見られるは当然。されど演奏する側からすれば、同じ事を繰り返せば飽きるは当然にして、King Crimson解散直後のRobert Frippのインタビューにしろ「『21st Century Schizoid Man』の演奏を強いられると云う悪夢に毎夜魘された」とあれば、私も演奏する側の端くれ故に、その心中察して余りある。故にRolling Stonesの如き人生金太郎飴の如くお馴染みのレパートリーを数十年も演奏し続けねばならぬとは、常軌を逸しておりまさしく狂気の沙汰なり。
さてここで再びDeep Purpleの新譜である。あの70年代の汚らしきファッションやその音作りも、全ては「当時」と云う意味の下でこそ成立し得れしものなれば、21世紀となりし今、彼等にとって当時より続く現在進行形の「新しい音」とは、このアルバムにて聴き得るこの音にこそあらん。現在の彼等のファッションにした処で「なんちゅうセンスやねん!」と嘆きたくもなるあられもなき姿なれば、そもそもデブにしてハゲたるは経年劣化故に致し方なしとすれど、これが嘗ての憧憬のロックスターの成れの果てと思えば、何とも悲しくなる事頻り。そもそも60年代末から70年代中頃までのロック全盛期を、微妙な年齢差にて追体験としてのみ知り得る私からすれば「ロックは長髪」なる黄金律が存在しており、長髪にあらぬロッカーなんぞ原則として許されざる者なり。斯くも思えば、今だ長髪にブラックレザーと云う出で立ちのBlack Sabbathの面々やMotorheadのLemmyなんぞは、まさしく親爺ロッカーの鏡にして尊敬に値し得らん。
されど矢張り「当時」に生きし彼等にすれば、汚らしき長髪にベルボトム加えてロンドンブーツなる姿は、単に当時流行のファッションにか過ぎず、頑なにそのファッションを貫く御仁もおられるが、殆どの御仁は気が付けば短髪にスーツ姿、ロックミュージシャンと云うよりも、何処ぞの悪趣味なる成金の如し。また楽器メーカーとのモニター契約等によるものならん、大抵は昨今の妙なデザインのギターなんぞを抱えておられれど、矢張り所謂スタンダードなストラトキャスターやレスポールなんぞ抱える方が、ロックミュージシャン然として見ゆるは、単に私個人のロック幻想に起因せしものなるか。されど一方でオヤジロックを愉しむ世のオヤジ共こそ、その財力に物を言わせ、また当時はあまりに高価にて高嶺の花たりしビンテージ楽器群を、今こそと云う訳で携えておられるそうで、まあそれもよろしかろう。如何せん私はビンテージギターなんぞ全く興味なく、安物ギターばかり使っておれば、そもそも60年代や70年代初頭のギターと云えど、当時それらは全く新品にしてビンテージにあらず、なれば当時は当然ビンテージ特有の音にあらじと思えれば、何故今更ビンテージギターを使わねばならぬや。さりとて昨今の妙なギターは許されざる代物なれば、結局はそれもロックに対する幻想なるか。
ならば今や五十路から六十路を迎えし歴々の親爺ロッカーに対して「昔は良かったのに、今のザマは何やねん!」と、悪態を突くなんぞ全く以て筋違い甚だしく、私の如き或る種懐古趣味的思惑抱く者からすれば「何であのカッコ良かった頃の音楽をずっと演らへんねん!」と、身勝手な憤りさえ感ずれど、確かにRolling Stonesの如く、若かりし頃に作りし曲を死ぬまで演奏し続けねばならぬは、ミュージシャンにとって或る種の極刑に等しきと思えればこそ、現在も尚「新しい音」を追究せんとする当人達にとって、何とも不条理且つ迷惑極まりなき言い分たらん。
されどである、客観的に考慮せし処で、矢張り「当時」の音には、何らかのマジックやら奇跡が内包されしは疑うまでもなく、故に昨今どころか70年代後期以降のロックと呼ばれるものを聴きし処で、一切何の感銘を受ける事もなく、たとえ楽曲が優れていようが、それら何かしらのマジックやら奇跡やらは既に失われし事明白なり。
私が思う処を述べれば、ひとつには録音技術の変化もあろう。録音技術は今や恐るべき進化を遂げておれば、60年代や70年代初頭のそれとは、既に全く別次元に到達せしと云えようか。またデジタル・マスタリングの技術により、音質向上への拘りもいよいよ究極へ到達せんとしておれど、では何故に私はそのデジタル・マスタリングされ音質向上されし音に、一切の感銘を受けぬのか。アナログ盤にて聴き親しみし愛聴盤であればこそ尚、デジタル・マスタリングされしCDの音に違和感を感ずるばかり、如何にしても嘗て感ぜしマジックや奇跡の如きが聴こえぬ次第。即ち音質の向上がそのまま音楽の向上とは等しからず、各楽器の分離が良くなればなる程に、嘗て感じ得れし渾然一体となりしカオスの如きは失われ、美術に於ける「捨て色」同様「捨て音」とでも呼ぶべき「聴こえなくていい音」も必要ではなかったか。されどデジタル・マスタリングの音にて育ちし世代にすれば、それでは心地良い音にあらずどころか「音が悪い」と一蹴せんとする処、矢張り私にとっては耳が痛む程の高域や不必要な程の低域が、大凡彼等には必要ならん。さすれば彼等と私とは、同じ音を聴きしにせよ、多分聴こえ方も大きく異なるのであろうし、故に心地良き音響等も異なるのであろう。どちらが優れしか若しくは正しきかなんぞ、それこそ各々の価値観なれば、語るは全く以て不毛にして、私は私で自らが信ずる音を選ぶのみなり。
さてもうひとつは、ミックスのバランスなり。何故昨今の音楽は、ああもドラムが喧しいのか。CDは勿論の事、ライヴサウンドにせよ同じにして、何故エンジニアはあれ程までにドラムを強調したがるのか。ダンスミュージックならばいざ知らず、ロックはギターが一番音デカいって決まってんのじゃ!このボケ共が!そもそも何も判っておらぬアホなエンジニアに限って「君のギター喧し過ぎだから音量下げて!これじゃあバランス取れないから…」と、アホな事ヌカして寄越す始末。私が幾ら「アホか!どんなにギター喧しかったって、マイクで拾ってんねんからドラム絶対聴こえるわ!バランスはワシらが取るから、お前は何でもええから卓のフェーダー全部目一杯まで上げとけ、ボケがぁ~!」と反論すれど、馬耳東風ならぬ愚耳東風か。嘗てのロックは斯くもドラム喧しくなければ、一体いつから斯様なミックスが一般になりしか。AMTの作品に於いては、殆どドラムが聴こえぬ程のミックスさえあれど、されど結果的にドラムは必ず聴こえ得るものなり。勿論明快には聴こえねども、では明快に聴こえねばならぬ必要もあるや否や。旧きロックのアルバムを聴いておれば、時折ベースラインやドラムは、音量も小さく不明瞭にして、何ともそのプレイをコピーせんとする者を泣かせしものなれど、ではそれが「音楽として」マイナスかと云えば斯くあらず。それどころかそれ故にこそ、あの音に依るマジックやら奇跡を生み出し得しではなかりしか。個人的にリズムが全面に強調される音楽を好まぬ由縁もあろうが、ドラムは分相応を弁え喧しくなき程度こそ心地良けれ。
或る種のミュージシャンは、何故「新しい音楽」と称する「誰もやってない音楽」なるを求むるか。そもそも「新しい」と云う事に、音楽的に一体何の価値があるのか。音楽が評価される場合「新しい / 古い」にあらず「良い / 悪い」若しくは「好き / 嫌い」にて評価されて然るべきなり。極論を云えば「新しい音楽」なんぞ発せられし刹那、既に「古くなる」に相違なし。また「誰もやってない」とは何とも滑稽なコンセプトなり。仮にスタンダード曲を10人が各々演奏すれば、絶対に些かなりとも各々異なるは当然にして、即ち誰も他人と同じ演奏なんぞし得る事叶わず、なれば何人なれど自分と同じ演奏するも叶わず。これこそ「誰もやっていない音楽」に相違なしや否や。況してや「誰もやっていない」事が、音楽にとって然程たりとも重要ならんや。何にせよ何とも度量の狭い話なれば、別にええやんけ、誰かが同じような事やってても!されど他人と異なる事、即ち所謂「自分の個性」を主張せんとすればする程、発せられる音は他人と似通い、常々他人を意識しチェックせねばならぬとは、何ともお粗末極まりなし。昨今の所謂「新しい音楽」が面白き試しなく、単に先端技術を駆使せしツールのみが新しかれば、その肝心の音自体は全く以て新しからず、況してや良くもなければ糞以下の如き代物なれど「新しきと云われるものを理解出来ねば、周囲からアホと思われる」なる愚の骨頂極まりなき風潮あればこそ、実は全く何が良いのか理解出来ずとも、矢鱈と有り難がる始末なり。
そもそも私なんぞ専門的音楽教育なんぞ一切受けておらねば、音楽活動を開始せし刹那より今に至るまで全くの我流故、当時自分達では自分達の音を「Deep Purple + Stockhausen」と思い込みておれども、当然斯くの如き音楽を演奏する技術も楽器さえも持ち合わせておらず、出来上がりし代物は結局誰にも理解される事なし。即ちこの私の音楽は、当時流行せしパンク・ニューウェイヴやノイズにあらず、また所謂ハードロックやプログレにもあらず、当然ジャズや現代音楽の類いでもなければ、結局カテゴライズ不能にして説明不可、それは或る意味「新しい」と云えぬでもなけれど、当然私にとっては斯様な思惑を以て演奏せしものにあらず、単に自分が好みしDeep PurpleとStockhausenを合体(融合にあらず)させれば、より一層好きな音楽となるのではあるまいかとの短絡的思惑のみによるものなり。
それから20年以上を経て、それら私の最初期の録音物は、イタリアのQBICO RecordsよりLPにて次々とリリースされ、セールスも至って好調にして評価もされれば、これこそ俗に云う「早過ぎた」だけの事なるか。即ち巷にて「新しい音楽」なる胡散臭き代物にて理解や支持を受ける御仁達は、どうあれ「新しい」と云うコンセプトの下、時代の流行と見事合致せしに他ならず、それは或る意味詭弁者と呼べるやもしれぬ。あまりに時代から異端的であれば理解されず、理解や支持を受けられぬ代物は「新しい」との烙印さえ押して貰えぬは当然、故に「新しくあらん」とすれば、常に時代の風潮や流行を的確に捉えておる事こそ絶対的命題なり。私の如く、情報化社会に身を委ねつつも情報に対し殆ど全閉状態なれば、当然時代を読むなんぞと云う器用な真似出来る筈もなく、結局は「古臭い時代遅れの醜い音楽」を演奏し続けるのみか。
先日運転中に拝聴せしラジオにて、Ian Gillanの新譜「Gillan’s In」が特集されておれば、思わず音量を上げ聴き入りし。本作は、彼の音楽生活40周年を記念してのセルフカバー・アルバムだそうで、彼が在籍せし歴々のグループ、Episode SixからDeep Purple、果ては1作のみ参加せしBlack Sabbath、加えてソロバンドたりしIan Gillan Band (Gillan) の曲に至るまでを、新旧のDeep Purpleのメンバーを含む豪華ゲストと共に録音し直せし代物とか。先ず拝聴せし「Smoke On The Water」に至っては、仮にも現在のDeep PurpleのギタリストたるSteve Moseのまるで素人ギタリストの如きお粗末なプレイに依り、イントロのあのリフの格好良さが皆無にして、結局あのシンプルなリフを斯くの如きロック史上に残るリフにまで昇華させしRitchie Blackmoreの偉大さを痛感させられるのみ。更に「Speed King」に至っては、私にとっては何とも劣悪なる録音にして、特にドラムの音がまるで陳腐なリズムマシーンの如きにて、久々に奮闘せしIan Paiceのドラミングも台無しなり。まあIan Gillanの音楽生活40周年を祝うべくパーティーの如き代物と思えば、そもそも一切文句を垂れる必要もなけれども、されど何故わざわざ格好悪くセルフカバーせんとするかの如き、全く以て斯くも酷いアレンジと録音なるか。この作品に至っては「新しい音」を追究する必然性さえなければ、些かなりとも「古臭い」音にしてもよろしかろうと感ずれど、矢張りそこはIan Gillanの現在進行形のミュージシャンたらんとする拘りか。「当時」を生きし偉大なるロックミュージシャンの歴々にとっては、今もって現在に於ける主流たらんとする意気込み溢れておられるのであろうが、彼等が音響技術の進歩と共に捨て去りしものこそ、実は彼等が為し得た最高の宝ではなかったか。
これもまた懐古趣味的ロック幻想を抱くオヤジの小言か。されど実際「古臭い」音を愛する御仁も多ければ、そこにも何かしら「音楽の真実」は在ろう。なれば私は矢張り、所謂「音質の悪い」作品群を輩出し続けんとし、いつの日か音楽が音響技術を超越する事を祈りたきものなり。
(2007/1/10)